「おくりびとの学習で取り組みやすい言語活動は何?」
教科書にある「読んで考えたことを伝え合う」という言語活動を、
より具体的な言語活動にして魅力的な単元にしていきましょう。
今回は小学5年生で学習する文学作品「おくりびと」(朽木 祥 作 光村図書出版『国語五年』)にぴったりな言語活動の紹介です。
今回、おすすめしたい言語活動が、
手紙を書く
という言語活動です。
え?手紙?
と思った方もいらっしゃると思います。
手紙という言語活動は使いやすく、取り組みやすい活動ですが、やはり奥深いですね。
メールやLINEなどが普及した今、手紙を書くことってほとんどないのではないでしょうか。
でも、わざわざ便せんに手書きで書く手紙には、
言葉選びの繊細さや手書き文字の丁寧さが求められます。
だからこそ、手紙を書くという言語活動には大きな意味があると思います。
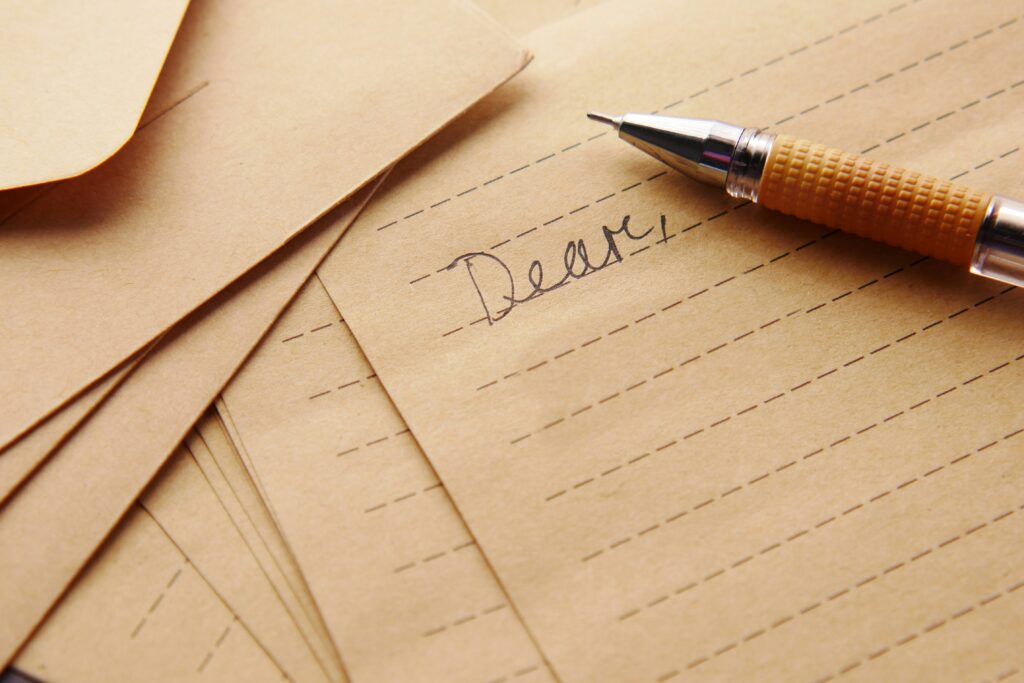
この単元で身に付けてほしい力は、
物語の全体像を想像すること
です。
この単元のねらいを、手紙を書くという言語活動でどうやって達成していくのか、
そのために、押さえておきたいポイントが3つあります。
ポイント1 手紙の設定をはっきりさせておく
ポイント2 段落構成を指定する
ポイント3 お互いの手紙を読む時間をとる
 でりぐ
でりぐこの3つのポイントを押さえると、グッと深い学びになりますよ。
言語活動「綾からアヤへ」
手紙を書く
誰でもが「手紙」と聞いて思い浮かべることができます。
文章で、相手に思いを伝えること。
でも、「誰が誰に書くのか」という部分で大きく変わります。
ここでは「綾からアヤへ」という設定にするところがポイントです。
ポイント1 手紙の設定をはっきりさせておく
ポイントの1つ目は、「手紙の設定をはっきりさせること」です。
「設定をはっきりさせておくってどういうこと?」と思われるかもしれませんね。
ここでの手紙の設定をはっきりさせるとは、
誰が書く手紙なのか、誰に宛てて書いた手紙なのか、いつ書いた手紙なのか、
といったことをしっかりと示すということです。
この設定をはっきりさせておかないと、ねらいとしているところに迫っていくことができません。
この単元でのおすすめの設定は、「綾がアヤに物語の最後の場面の後に書く」というという設定です。
この作品は主人公である綾に同化しやすく、
綾の視点で作品の鍵となっているものの意味やその役割を読んでいくことで、
作品の全体像に迫っていくことができると思います。


ポイント2 段落構成を指定する
ポイントの2つ目は、「段落構成を指定すること」です。
言語活動の目的は、その活動を通して目標とする資質・能力を身に付けることです。
このようなねらいがあり、それを達成することを目指して試行錯誤することが学習です。
今回は、「作品の全体像を想像すること」が目標としてありますので、
その目標に迫っていけるような手紙を書くという活動にしなければならないので、
自由に書けばOKではなく、指定することが必要になるわけです。
では、どのような内容と構成を指定するのか。
私であれば、以下のような段落構成を考えます。
1段落 「アヤ」へ伝えたいこと
2段落 「アヤ」へつながる具体的なエピソード1
3段落 「アヤ」へつながる具体的なエピソード2
4段落 これからの私
イメージしやすくするために、1つのモデルを書いてみました。
このような感じで書けるといいですよね。
ですが、文字数などは子どもたちの実態によって、
調整が必要だと思います。
言語活動のイメージはもっていただけたでしょうか。



教師が一度、書いてみると、単元づくりにとても役に立ちますよ。
ポイント3 お互いの手紙を読む時間をとる
ポイントの3つ目は、「お互いの手紙を読む時間をとる」ことです。
この手紙を1人で書くとしても、
自分自身と対話を何度も繰り返し、
さらに作品とも何度も対話をします。
しかし、教師や友達と読み合ったり、対話したりすることで、
視点が広がったり、深まったりします。
いつでも対話できるような環境を作っておくことも大切ですが、
意図的に手紙を読み合ったり、意見交換する時間を設定することも大切です。
タイミングも書き終わった時に限定せず、
書き出す前、書いている途中で、
教師が意図をもって対話する時間、読み合う時間を作って対話させることで、
充実した言語活動になることは間違いありません。


まとめ
今回、「おくりびと」のおすすめ言語活動として紹介したのは、
手紙を書く
です。
そのためのポイントを3つ。
ポイント1 手紙の設定をはっきりさせておく
ポイント2 段落構成を指定する
ポイント3 お互いの手紙を読む時間をとる
どれだけ深く読めているかによって、手紙の重みが変わってくるような気がします。書いたことに感動できるようにしたいですね。



自分で書いて、読み返した時に「なかなかいいじゃん」と子ども自身が思えるといいですよね。
言語活動をうまく進めるためには、教材分析をしておくことは欠かせません。
以下の記事では「教材分析はなぜ必要なのか?」について解説しています。
もちろん、おくりびとの教材分析もありますよ。


他にもおすすめの言語活動を紹介しています。
そちらもぜひ合わせて読んでみてください。


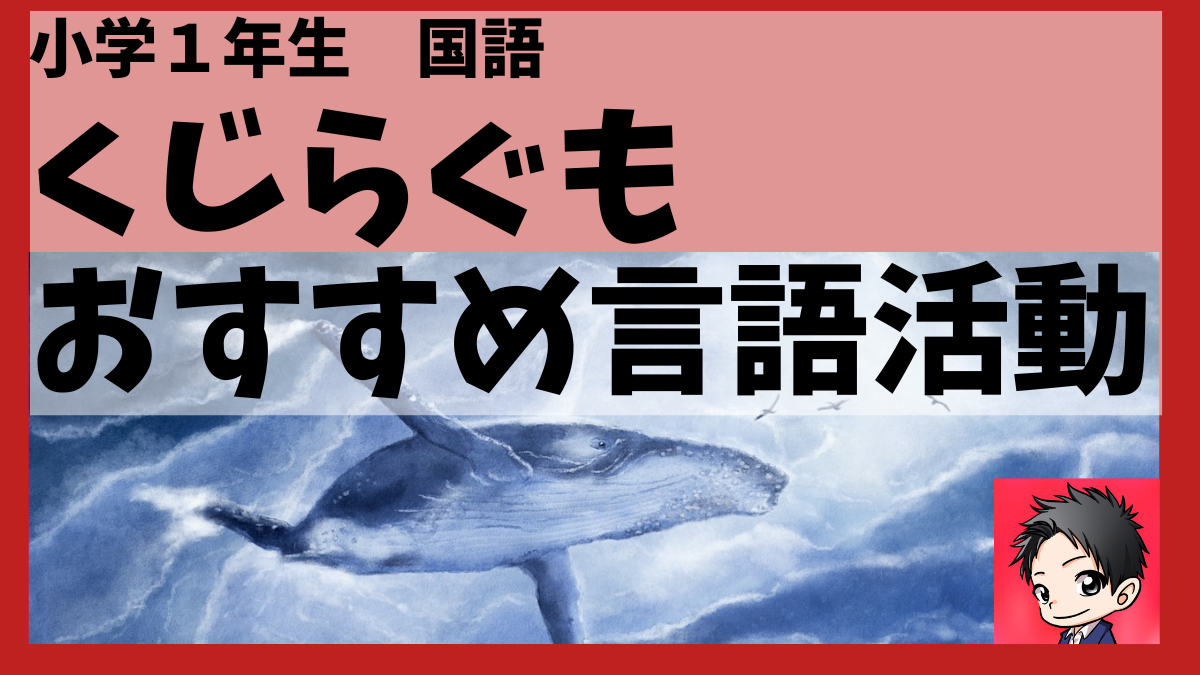
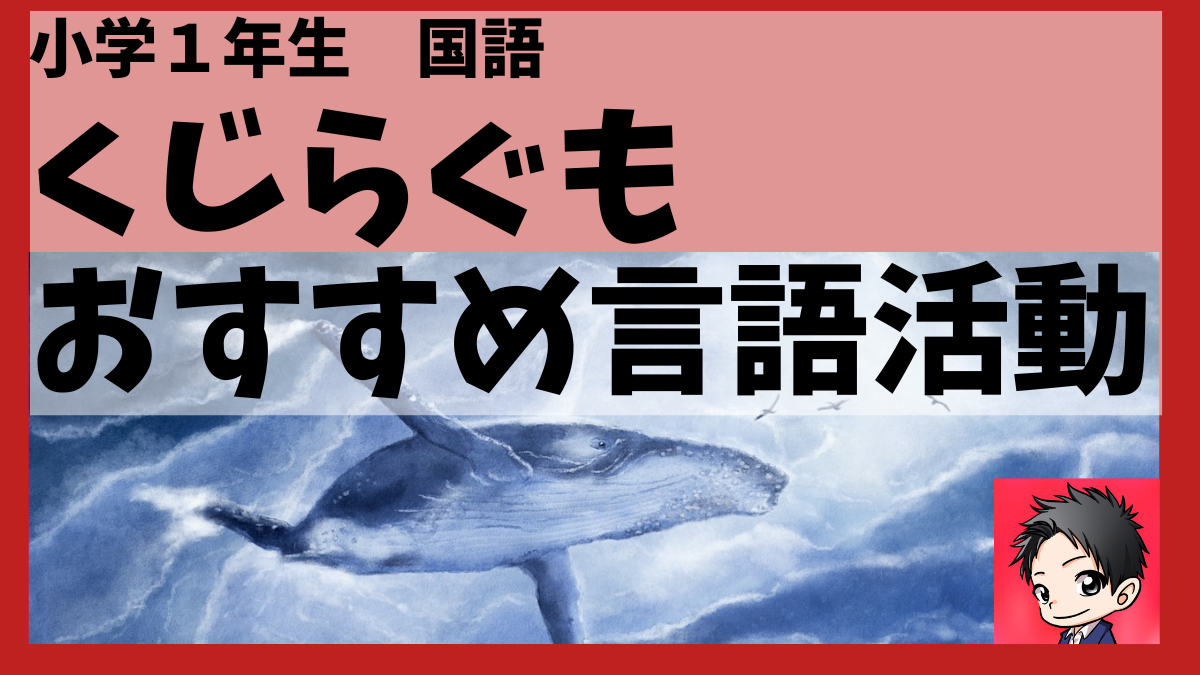
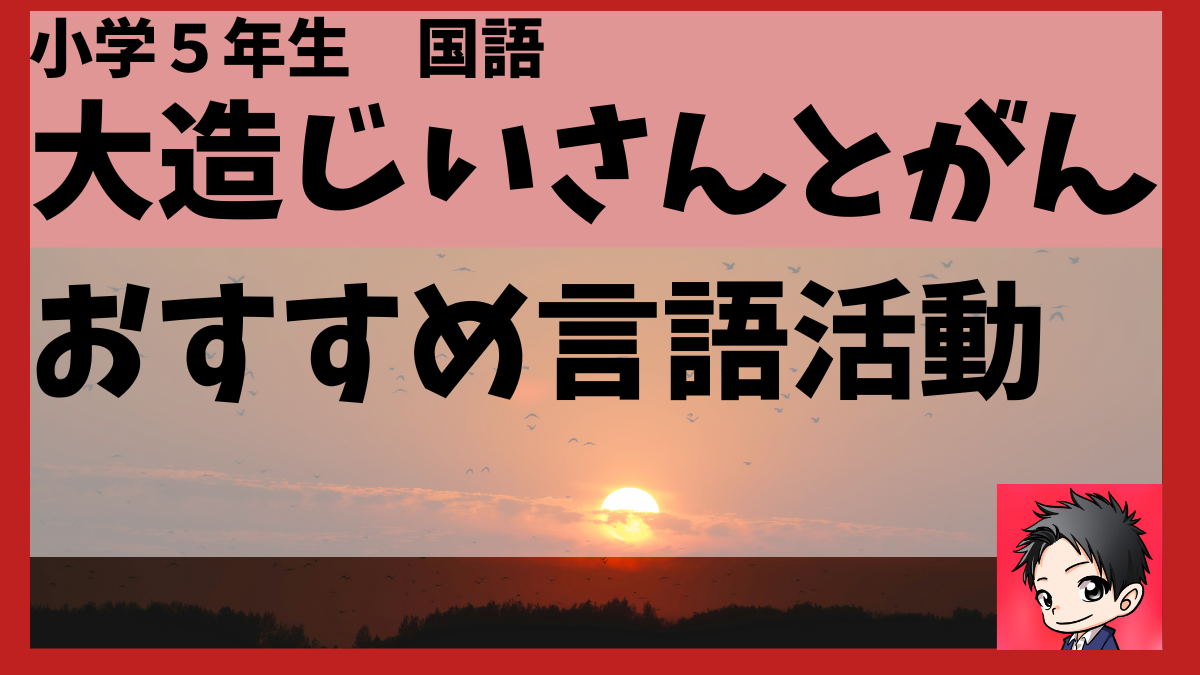
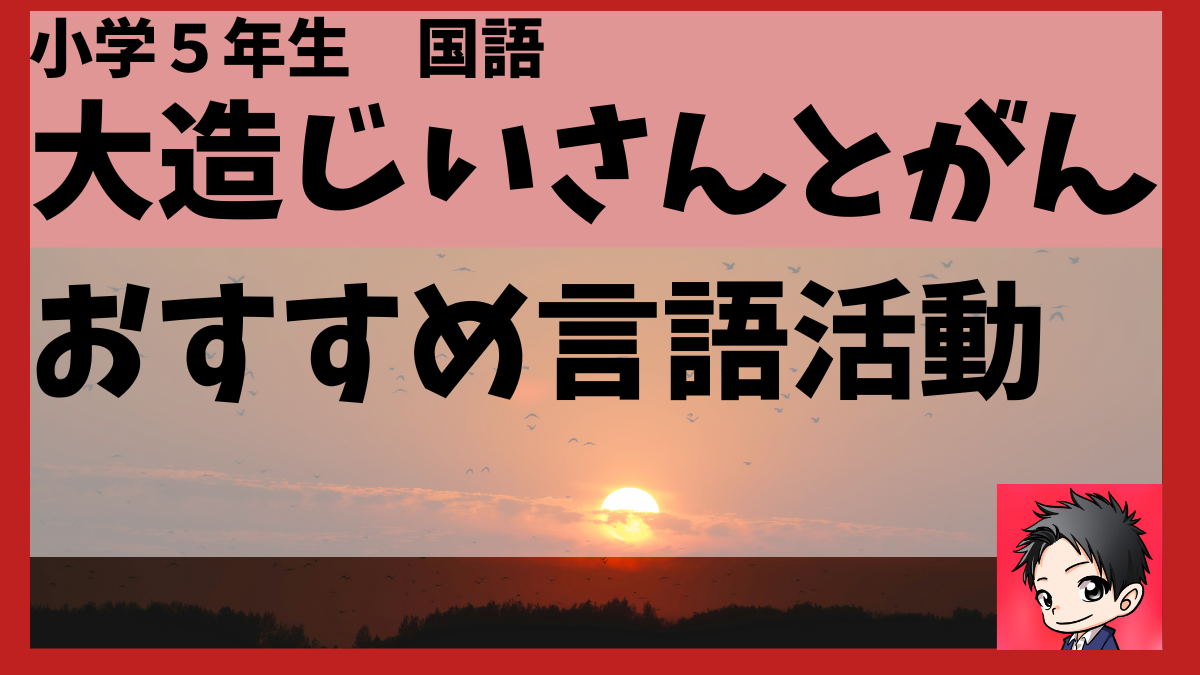
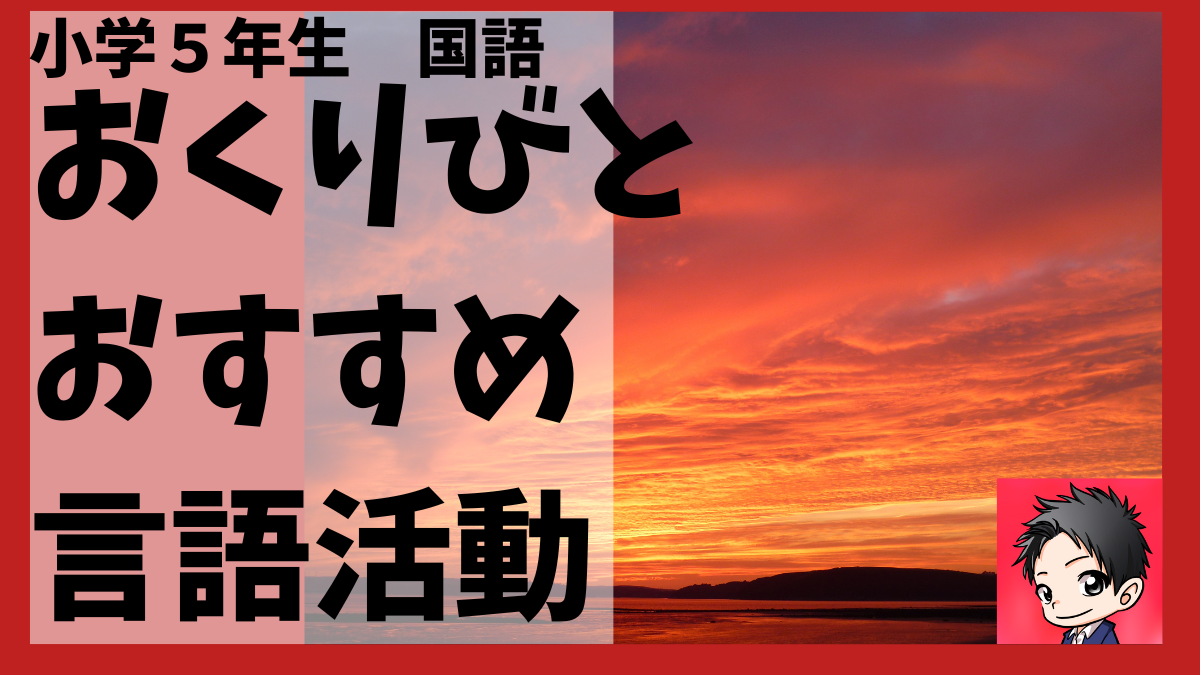
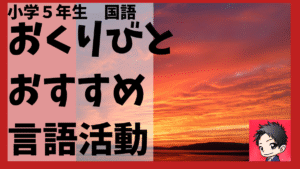
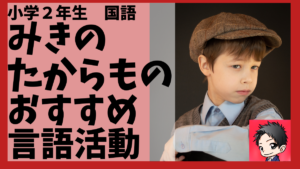
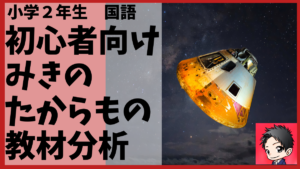
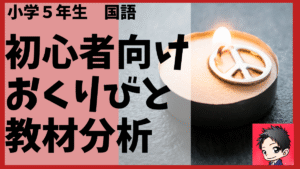
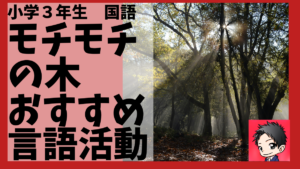
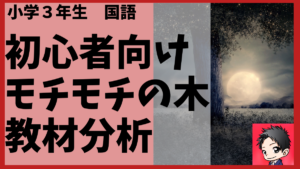
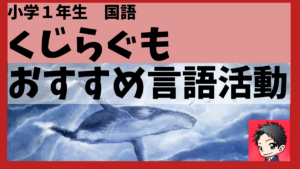
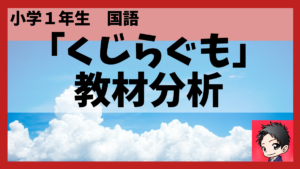
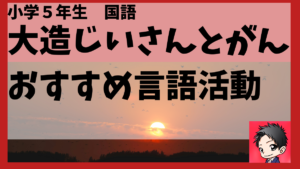
コメント