光村図書出版のホームページに、次のような資料がありました。
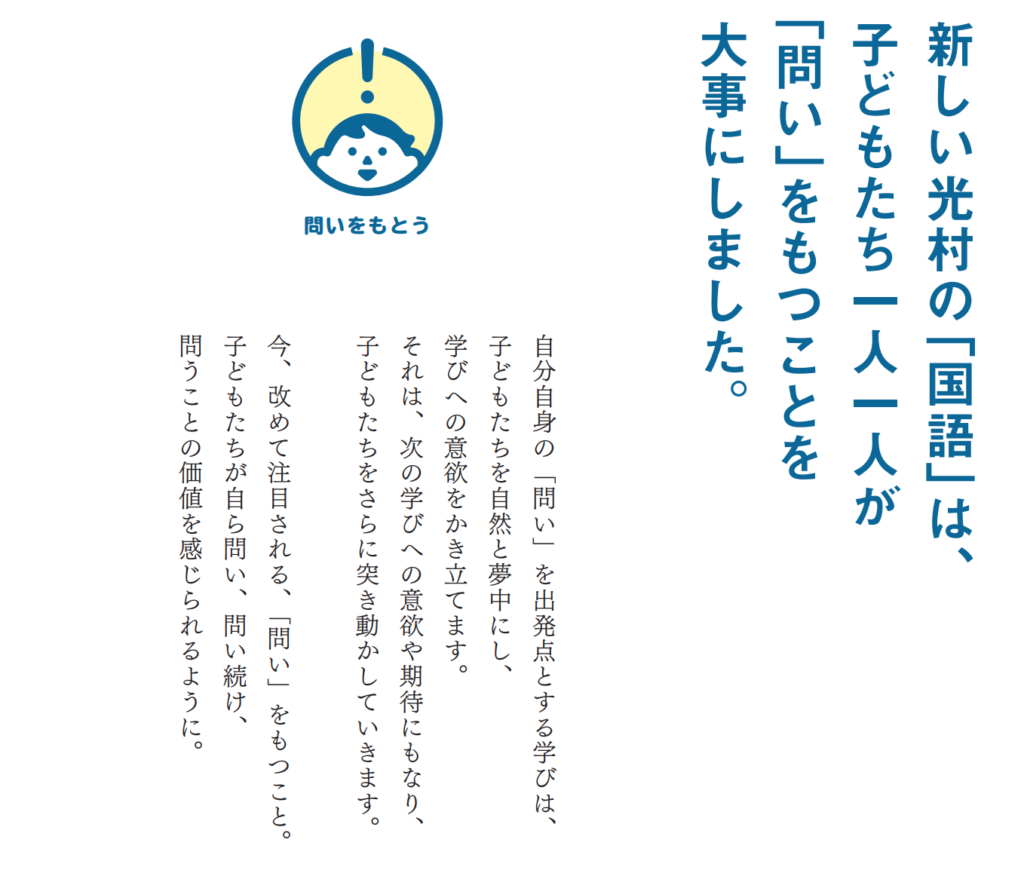
(引用:光村の「国語」完全活用ガイド 子どもの思いを学びにいかす「問いをもとう」)
主体的・対話的で深い学びの実現を目指す、今の日本の学校にとって、
「子ども自らが問いをもつ」ことはその実現にとって大きな意味があると思っています。
では、「子ども自らが問いをもつ」ことの意味や価値について少し考えてみたいと思います。
 でりぐ
でりぐ今日の話は少し難しいですが、とっても重要です!
子どもが自ら問いをもつ学びとは?
子どもたちって(子どもに限らずですが)、身の回りの出来事や授業の中で、ふとした疑問や興味を抱きますよね。
この「問い」こそが、子どもにとっての学びの出発点なのです。
自ら問いをもつということは、単に質問をすることではなく、
「もっと知りたい」「確かめたい」「どうしたらいいのだろう」と、
自分の感じたことや知識とのギャップから自然に生まれる疑問をもとに、学びに向かうことです。
例えば、
「植物はなんで光が必要なの?」
「どうして昔の人はこんな道具を使ってたの?」
「この主人公は本当に正しいことをしたのかな?」
こうした自らもった問いは、知識を「受け取る」のではなく、自ら「獲得する」学びへの入口となります。
それでは、自ら問いをもつことの意味や価値について考えてみたいと思います。


主体的・能動的な学びを促す
自分がもった問いを中心に学ぶことで、子どもは自ら学びを進める力を育てます。
教師の指示を待つのではなく、自ら情報を集め、考え、友達と話し合い、答えを見つけ出そうとするようになります。
具体的には、
自ら本やインターネットなど、活用できるツールを活用しようとする
実際に実験や観察など、行動を起こしてみる
人に聞いてみたり、情報収集しようとしたりする
こうしたプロセスの中で、「自分の学びは自分でつくるもの」という感覚が育まれます。
1つ1つの理解が深まる
自らの問いを追究する過程では、単なる暗記ではなく、
「どうしてそうなるのか」「他にもどんな考え方があるのか」といった深い思考が求められます。
例えば
「昼と夜があるのはなぜか?」という問いに対して、
→ 地球の自転を調べる → 実際に地球儀やライトで確かめてみる → 誰かに説明できるまで考える
このようにして、知識が「自分の言葉」で語れるレベルまで落とし込まれることで、
表面的でない、本質的な理解が得られることが期待できます。


対話や協働の力を育む
問いは一人ひとり違って当然ですし、むしろそれ良いものです。
友達と問いを共有し合う中で、他の子どもの視点や考え方に触れる機会が生まれます。
例えば、
「〇〇さんはこんなこと疑問に思ったんだ!」(自分と同じだったor自分とは違っていた)
「それ、私も知りたかった!」(他者の問いが参考になる、言語化してもらえる)
「僕の考えとはちょっと違うかも」(他者の異なる問い、考えに触れる)
こうしたやり取りの中で、多様な価値観や視点を認め合い、学びを豊かにする力が育っていきます。
自分とは違う問いや答えに出会うことで、視野も広がりますよね。
未来につながる力を育む
予測することが困難な現代社会では、「正解のない問い」に向き合う力が求められています。
自ら問いをもち、試行錯誤しながら学ぶ経験は、将来、未知の課題に直面したときの対応力となります。
例えば、
社会課題に向き合う「探究的な学び」や「持続可能性を検討するSDGs学習」などとつながります。
また、将来のキャリアに必要な「課題発見力」「情報活用力」「表現力」などを育成することにもなりますね。
つまり、「自ら問いをもつ学び」は、学力だけでなく、
これからの社会を生き抜く力そのものを育てる土台となります。


まとめ
今、求められている主体的・対話的で深い学び。
その実現には「自ら問いをもつ力」は不可欠です。
その価値として、
1 主体的・能動的な学びを促す
2 1つ1つの理解が深まる
3 対話や協働の力を育む
4 未来につながる力を育む
他にも問いをもつことへの価値はあると思います。
ぜひ子どもの「自ら問いをもつ力」を育んでいきましょう。
そうすれば、子どもの学びの姿、そして、教室の風景が変わってくるはずですよ。



子どもが問いをもてるようにするための学習も必要ですね。そのお話もしていきたいと思っています。
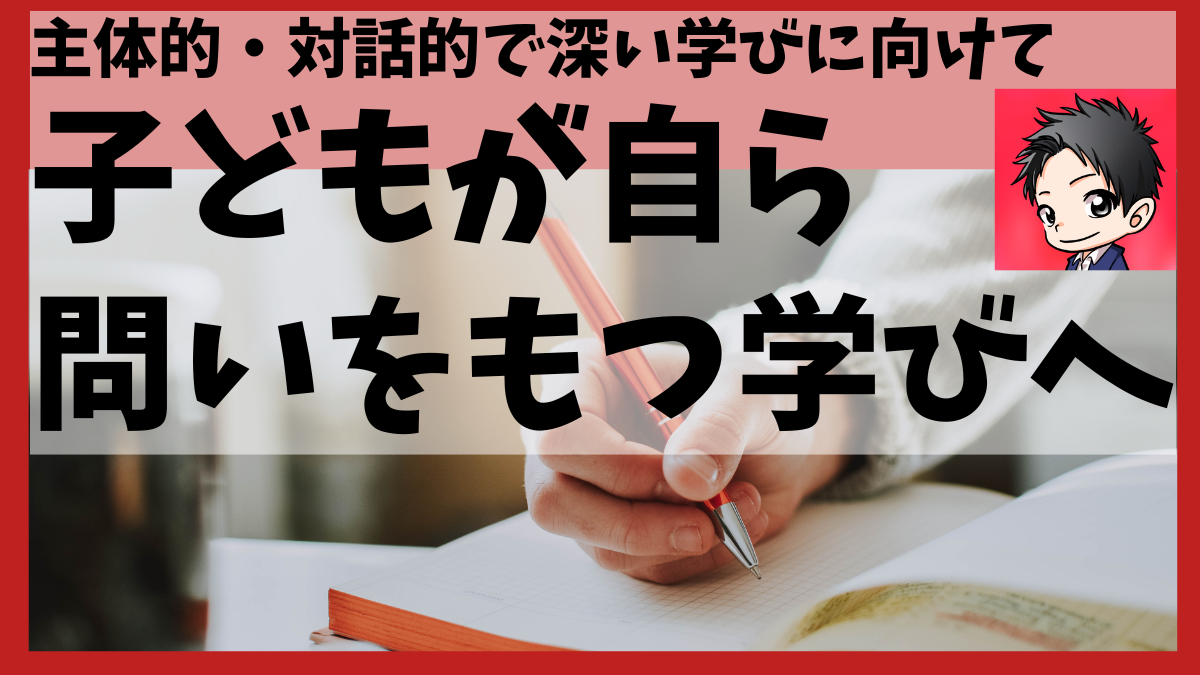
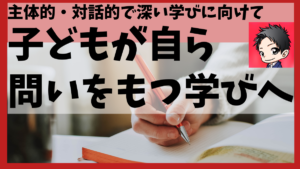
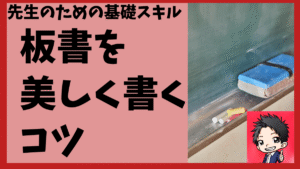
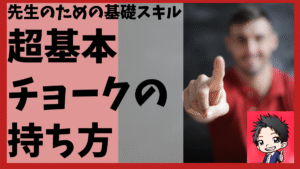
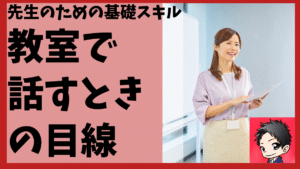
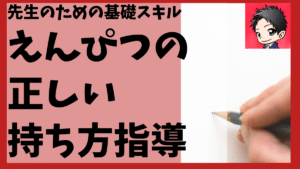

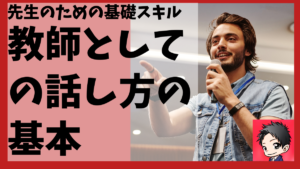


コメント
コメント一覧 (1件)
[…] でりぐの国語教室 子どもが自ら問いをもつ学びへ | でりぐの国語教室 光村図書出版のホームページに、次のような資料がありました。 (引用:光村の「国語」完全活用ガイド 子 […]